EVENT
2025.08.22に開催された地域版人的資本経営コンソーシアム(仙台会場)のレポートを公開します
2025年8月22日、仙台で地域版人的資本経営コンソーシアムが開催されました。今回のテーマは「人手不足の解消に向けた施策」。三井化学株式会社 取締役 専務執行役員 CHRO 安藤嘉規氏、株式会社つばめいと 代表 山後春信氏が登壇。国内外のグループ会社を束ねる大手メーカー、地域に密着した中小企業、異なる立場から人材採用・育成・定着・越境学習の実例を紹介しました。参加者による質疑応答や意見交換会を通じて「人材」に関する知見を深める機会となりました。
「東北エリアをwell-beingな雇用環境の創出の場に」東北経済産業局 古谷野氏

開会の挨拶で東北経済産業局 古谷野義之氏は「東北地方は少子高齢化が進み、若者・女性の首都圏への流出が進むエリア」と指摘。他のエリアに比べても人材の育成、確保、定着が喫緊の課題であり、人的資本経営の重要性を訴えました。経済産業省としても、セミナーの開催、人材のマッチング支援などで、地域企業の人材課題の解決を持続的に支援していくとのこと。地域版人的資本経営コンソーシアムでは、先進企業の取組事例を共有し、「人的資本経営をいかに実践し、どのように活用すべきか」の理解を深めるヒントになると語りました。
「深刻な人手不足を抱える中小企業こそ、多様な人材活用を」経済産業省 川久保氏
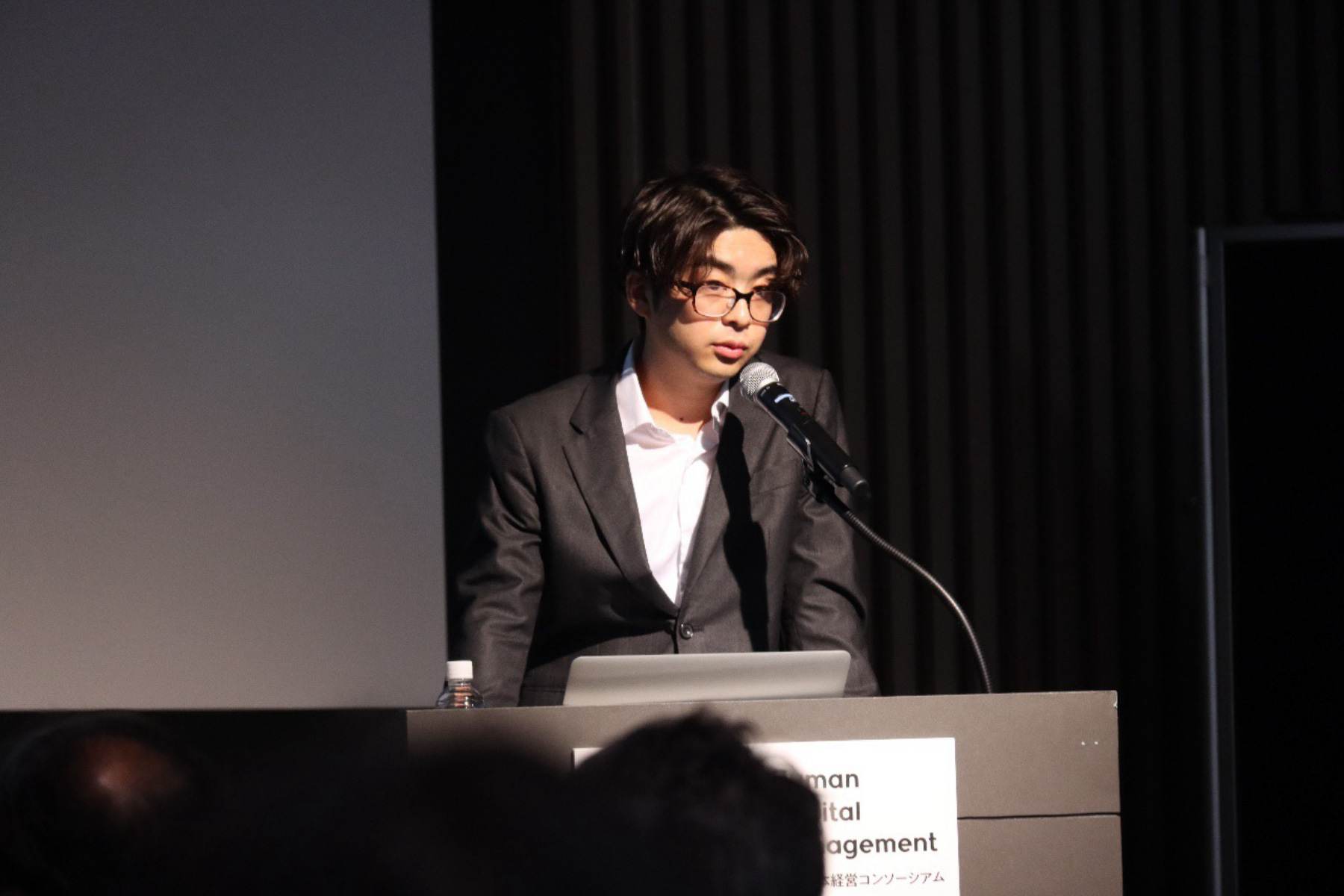
経済産業省 川久保俊氏は「参加企業を対象とした事前アンケートで半数以上の企業が人手不足に課題感を持つ」と述べ、人手不足の実態を紹介しました。さらに、こうした人手不足への対策として人材の採用に取り組んでも「応募がない」「応募者が自社の基準に合わない」といった現状を紹介した。そのうえで、人材不足を克服した中堅・中小企業の対応事例として、賃上げや働きやすい職場環境の整備、定年延長等の人事制度の構築に取り組む企業が多いことを紹介。特に、人材獲得・離職防止に向けた中堅・中小企業での取組状況として、中途採用の活発化や、人事制度の改定、副業・兼業人材の活用に取り組む企業が多いことについても解説しました。
「“企業間副業”が生み出す新たな価値」三井化学株式会社 取締役 専務執行役員 CHRO 安藤氏

創業110年を超える三井化学株式会社。合併・統合を経た自社の歴史から、安藤嘉規氏は「多様な人材の集合体であることが当社の強み」と述べました。同社では、経営戦略と連動した人材戦略を実施。新卒採用は地元志向・大学への進学志向の高まりを踏まえ、従来の工業高校卒中心から大卒・高専へと対象校を拡充。キャリア採用では社員紹介によるリファラル採用を重視し、母集団の拡大に努めています。
働き方改革の実例としては全社員を対象にしたエンゲージメントの調査と活用、テレワーク制度を導入。地域企業と連携した宮城県気仙沼市でのワーケーション、新潟県燕市での副業派遣、企業間相互副業(ソニーグループ株式会社・株式会社日立製作所との協働)の取組を紹介。「派遣企業には越境学習で新たな学びがある一方、受け入れ企業では多様な外部人材が活用できます」と企業と社員、双方にとっての価値を示しました。
「学生の拠点づくりと副業人材の活用。“地域の人事部”の挑戦」株式会社つばめいと 代表 山後氏
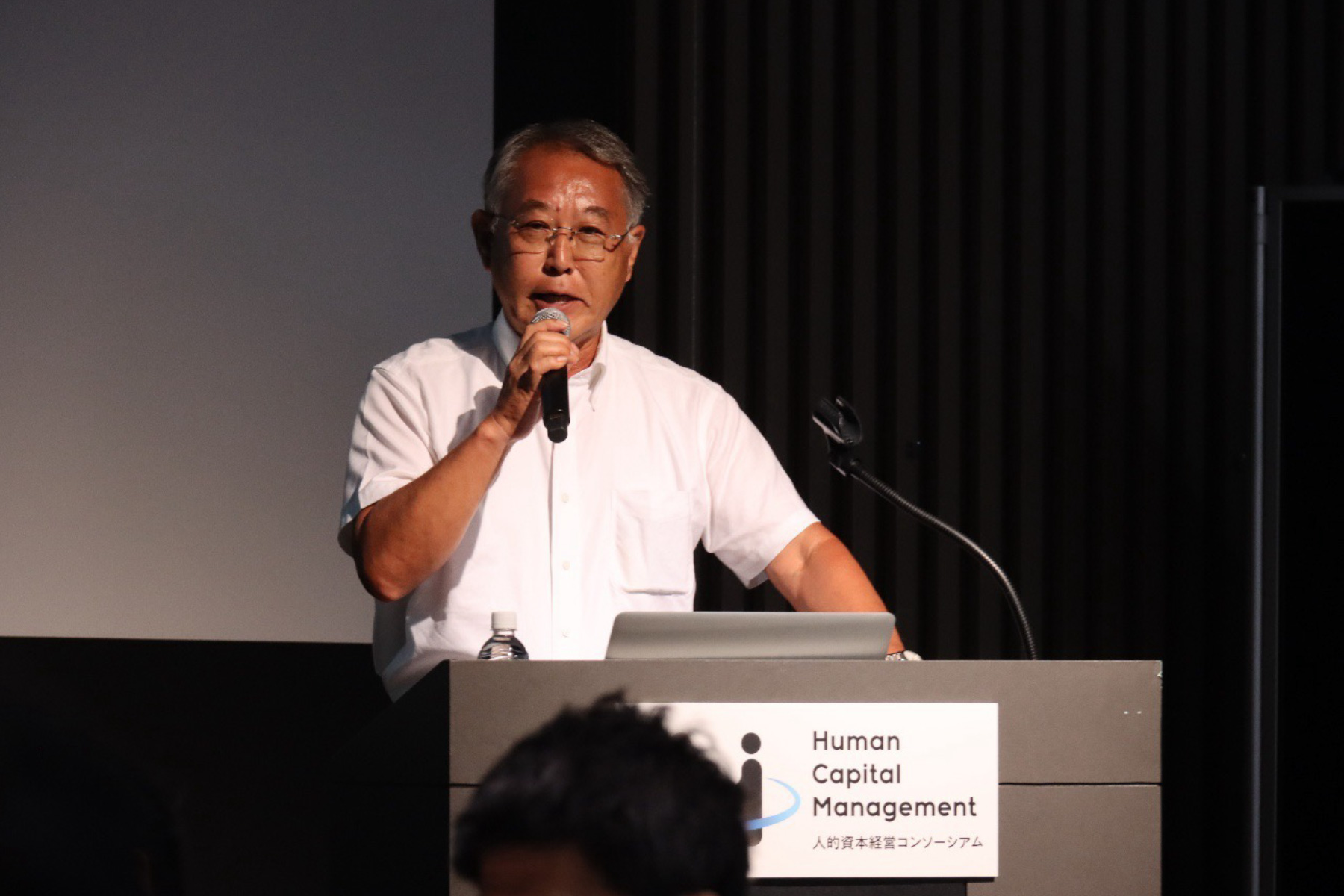
株式会社つばめいと 山後春信氏は、新潟県燕市で「地域の人事部@燕」を運営。中小企業と地域外での副業人材のマッチング事業を推進し、「自らの経験を活かして、経営に関する意思決定ができるのが小さな現場の面白さ」とそのメリットを語ります。
若手人材の流出が課題となっている同市での人材獲得を目指して、大学生のインターンシップの受け入れ拠点を開設。高卒採用研究会「TSUBAME FIND WORKS」にはインターン学生が参加するなど、学生と地域企業をつなぐことで地元企業の意識改革を後押ししています。地元企業を対象にした若手育成セミナーの開催、小規模企業・製造業の従業員向けの「標準型キャリアプラン」の作成、OJTマニュアルの開発などを実施し、人材獲得と育成に尽力。「人への投資で経営課題を解決する」ビジョンを掲げ、地域産業の発展に向けた展望を語りました。
人材戦略をめぐる質疑応答&意見交換会



講演後の質疑応答では、安藤氏と山後氏が再登壇。事前アンケートとあわせて参加者の質問に回答しました。「経営戦略と人材戦略の連動について」「グループ企業をまとめるには」という質問には、安藤氏から「人材戦略に関する施策はグローバルベースで連結。グループ各社の自主自律を尊重しながらも、本社がファシリテーションや支援を行っている」と自社の取組を紹介。
「ESGや地方創生との関係性について」の質問には、山後氏が「地方創生という言葉は使用せず、“自分たちの街をどうやって持続させるか”の視点で活動している」と回答。地元の経営者もESGには前向きに捉えていると続けました。ほかにも「副業マッチングと越境学習の成果」「大卒・高卒の現場職での人材確保」などさまざまな問いに向き合いました。
後半はテーブルごとに意見交換会を実施。参加者同士が「外国人材の登用」「若手とベテランのコミュニケーションの難しさ」について議論。各テーブルの代表者が発表を行い、課題を共有しながら学びを深めました。参加者からは「地域の課題解決の取組に感銘を受けた」「人材不足は全国共通の課題だと再認識した」といった声が寄せられました。
「人手不足という課題共有から、新たな解決策を生み出す」経済産業省 今里氏

閉会の挨拶では経済産業省 今里和之氏が登壇。「人口減少が進む中で人手不足は避けられません。これまで“コスト”と考えられてきた人材を“資本”として捉える発想の転換が必要」と呼びかけました。「同じ課題を共有することで新たなアクションやソリューションが生まれる」と、人的資本コンソーシアムの場を活用したネットワーク活用を提案。「経済産業省では、今後も地域の中堅・中小企業への支援を続けていく」と力強く締めくくりました。
今回の仙台会場では、地域企業ならではの課題とその実践例が数多く共有され、盛況の内に閉会を迎えました。